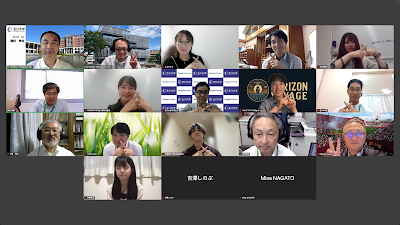こんにちは!玉川大学工学部マネジメントサイエンス学科の石川優理と申します。小酒井先生のゼミ生です。今回はxTalksの参加者として私がレポートを担当します。どうぞよろしくお願いいたします!!
今回のテーマは「玉川ブランドのお酒をつくろう!醸造と購買のプロと描く”玉川のお酒”の未来」でした。初めに、話題提供として、玉川大学農学部先端食農学科の佐々木先生より、日本酒を中心とした酒類の歴史や製造、そして酒類業界の現状と今後の課題について話してくださいました。 「お酒とは発酵物である」という基本的な考えから始まり、日本を含むアジア圏で古くから発酵食品が生活に根付いてきたことが紹介されました。日本酒は戦国時代から江戸時代にかけて一般庶民にも広がり、江戸時代にはまだ「菌」という概念がない中でも、人々が経験的に発酵の仕組みに気づき、酒造りを行っていたことが印象に残りました。明治時代以降は近代化が進み、清酒製造が科学的・体系的に発展していったとのことでした。
続いて、清酒製造の流れについて詳しい説明がありました。玄米を精米して白米にし、浸漬・蒸しの工程を経て蒸米を作り、麴菌による製麹、酒母の製造、そして蒸米・麹・水を三段階で仕込む「三段仕込み」によってもろみを作るという、日本酒特有の複雑な発酵工程より私の好きなお酒が造られているのだと学びました。アルコールを添加しない純米酒や純米吟醸酒といった種類の存在からも、日本酒の多様性を感じました。また、日本酒の種類について、吟醸酒、純米酒、純米吟醸、本醸造酒、普通酒などが紹介され、それぞれ香りや味わい、価格帯に特徴があることが説明されました。吟醸酒にはメロンやリンゴのような華やかな香りを持つものもあるというお話がとても印象的で、今度探してみたいと思います。
後半では、酒類業界の現状と課題について触れられました。国内需要は減少傾向にあり、単価の安い商品の消費は減っている一方で、高価格帯の商品は必ずしも減っていないことから、今後は「商品の差別化」や「高付加価値帯」が重要であると指摘されました。事例として、獺祭で有名な旭酒造の取り組みが紹介され、精米歩合を大幅に下げた超高級志向の商品開発や、他社には真似できないブランド構築によって成功してきた点が印象に残りました。また、日本酒の海外市場について、100兆円規模とも言われる世界市場に対して、日本酒はまだ0.1%にも満たないという現状を知りました。 さらに、酒造業界では蔵元の高齢化や後継者不足といった人材面の課題も深刻であり、AIやデータを活用した酒造りの重要性についても言及がありました。分析の事例などより、職人の勘に頼る酒造りから、データに基づく新たな酒造りへの移行の可能性を学ぶことができました。
途中のLTでは、倉橋さん、濱田さん、徳永さんからそれぞれ短時間ながらも豊富な情報提供をしてもらい、異なる立場や経験からの視点を知ることができました。一つのテーマでも、立場が変わることで捉え方が大きく異なることを実感しました。後ほどの座談会につながる話も多くありました。
話題提供者の二人目として、玉川大学購買部の中村課長より、「届ける側」の視点からのお話をしてくださいました。お酒を作るだけでなく、誰に、どのように届けるかという視点の重要性を改めて考える機会となり、玉川ブランドとしての価値をどのように伝えていくかについて深く考えさせられました。
最後に、後半のテーブル座談会では、「玉川ブランドのお酒」をどのような形で展開できるかについて、参加者同士で自由に意見を出し合いました。お酒そのものの案としては、果物原酒を使ったお酒や、葡萄酒などを用いた甘みのある酒、玉川で取れたポンカンやトマトといった身近な素材を使ったお酒などが挙げられました。学内で収穫された素材を使用することで、玉川らしさやストーリー性を持たせることができるのではないかという意見でした。 また、倉橋さんより微細藻類を活用したお酒というアイデアも出され、環境や持続可能性の観点からも、玉川大学らしい新しい取り組みになるのではないかという声がありました。これについては、いくらのような粒であり、いろいろな色にできるとのことでした。とてもきれいなお酒ができ、食感として海ブドウのような感じらしいので、できた際には是非味わってみたいと思いました。
さらに、ノンアルコールや低アルコールという視点も多く出ました。文化祭などのイベントでも提供できることや、子供やお酒を飲めない人も楽しめる商品があれば、より幅広い層に玉川ブランドを知ってもらえるのではないかという意見でした。その他に、玉川らしさを大事にした商品づくりとして、イエローコスモスをモチーフにしたお酒や、購買部で気軽に購入できる商品開発なども話題に上がりました。
以上より、今回のxTalksを通して、酒造りは単なる製造技術ではなく、歴史・文化・経営・流通・技術と複雑に結びついた総合的な取り組みであることを学びました。また、異なる分野の専門家や参加者と意見を交わすことで、多角的に物事を考えることの大切さを改めて実感しました。
お話ししてくださった皆さん、そしてこのような貴重な機会を設けてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。また、お話できたらとても嬉しく思います!!次回のxTalksも楽しみにしています!!
--------------------------------------------------------
xTalks Vol.33
玉川ブランドのお酒をつくろう!
— 醸造と購買のプロと描く“玉川のお酒”の未来 —
「もし玉川大学が“自分たちのブランドのお酒”をつくったら、何ができる?どんなお酒があったらうれしい?」
そんな素朴な問いから、大学発の価値創造を一緒に考えてみようという企画です。
今回のVol.33では、農学部の佐々木慧先生(発酵工学) に、原料・醸造方法・香り・法律的な縛りなど、“大学で作りうるお酒のリアル”を専門的にご紹介いただきます。
さらに、購買部課長・中村亨氏 に、キャンパスブランド商品の売れ方、学生・教職員・OB/OG の嗜好、そして購買動向といった“現場の視点”を共有いただきます。
醸造の専門知と、キャンパスブランド商品の現場知。
この二つが交わると、玉川大学らしい“ストーリーのあるお酒”が見えてくると思いませんか?玉川大学ならではのブランド創造の可能性に迫ります。
お酒に詳しくなくても大歓迎。
ブランド戦略・商品企画・大学発プロダクトに興味がある方は、ぜひご参加ください。
今回も、xTalksならではのゆるくて濃い議論を楽しみましょう。
--------------------------------------------------------
日時:2025年12月12日(金) 18:00-20:30
場所:Zoom
話題提供:
①佐々木慧先生(玉川大学 農学部 先端食農学科)
https://yumenavi.info/vue/lecture.html?gnkcd=g013182
②中村亨さん(玉川学園 購買部)
https://tamagawa-cs.jp/